【北陸農政局 輸出産地サポーター】東川直裕さん
人材の声
「北陸から世界へ、“おいしい”を届ける伴走者」
日本の“おいしい”を世界に届ける挑戦を後押しする「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクト。地域の食資源を生かしながら、輸出という新たな市場に挑戦する生産者を支えるのが「輸出産地サポーター」です。
今回は、北陸エリアでサポーターとして活動する東川さんに、これまでのキャリアや現場のリアル、支援に込めた想い、そして人材活用の可能性について詳しく伺いました。地域の未来を見据える“伴走支援”の在り方が、ここにあります。
【プロフィール】
東川 直裕(ひがしかわ・なおひろ)
- 農林水産省 北陸農政局 輸出産地サポーター
- 大手食品スーパーにて10年間勤務
- 経営コンサルティング会社(現、タナベコンサルティンググループ)にて22年間、中堅中小企業の経営戦略・経営体質改善・人材育成支援に従事
- 豆腐加工食品メーカーに転職し、輸出事業部をゼロから立ち上げて“がんもどき”を中心とした製品で海外展開を推進
- 2024年より現職。生産者、事業者に「寄り添う支援」をモットーに、北陸地方の、特に中小食品製造事業者を対象とした輸出支援を実施中
はじめに、これまでのご経歴について教えてください。
東川さん(以下、東川)
私は大学卒業後、食品スーパーに10年間勤務し、その後は経営コンサルティング会社に22年間在職していました。経営戦略や経営体質の改善、人材育成を中心に中堅中小企業の経営コンサルティングに携わってきました。その後、前職の先輩に誘われて、地元の豆腐加工製品を製造する会社に転職し、当時、社内では関心が薄かった“がんもどき”の輸出事業をゼロから立ち上げました。
豆腐(Tofu)は、海外でも健康食材として注目されていましたが、会社は「がんもどきなど輸出できるはずがない」と否定的。しかし、私は「知られていない食材だからこそチャンスがある」と考えて取り組みました。今ではその経験が、現職の輸出産地サポーターとしての原点になっています。
北陸地方の生産者、事業者を支援する上で見えてきた輸出の課題はありますか?
東川
北陸地方には調味料や伝統的な食品など、魅力的な産品は多いのですが、事業者の多くが「発信力」や「販路開拓」に課題を抱えています。特に小規模な事業者は、マーケティングやブランディングの視点が不足しており、「何から始めたらよいのかわからない」、「どうせうちの商品は売れない」と初めから諦めてしまうケースも少なくありません。
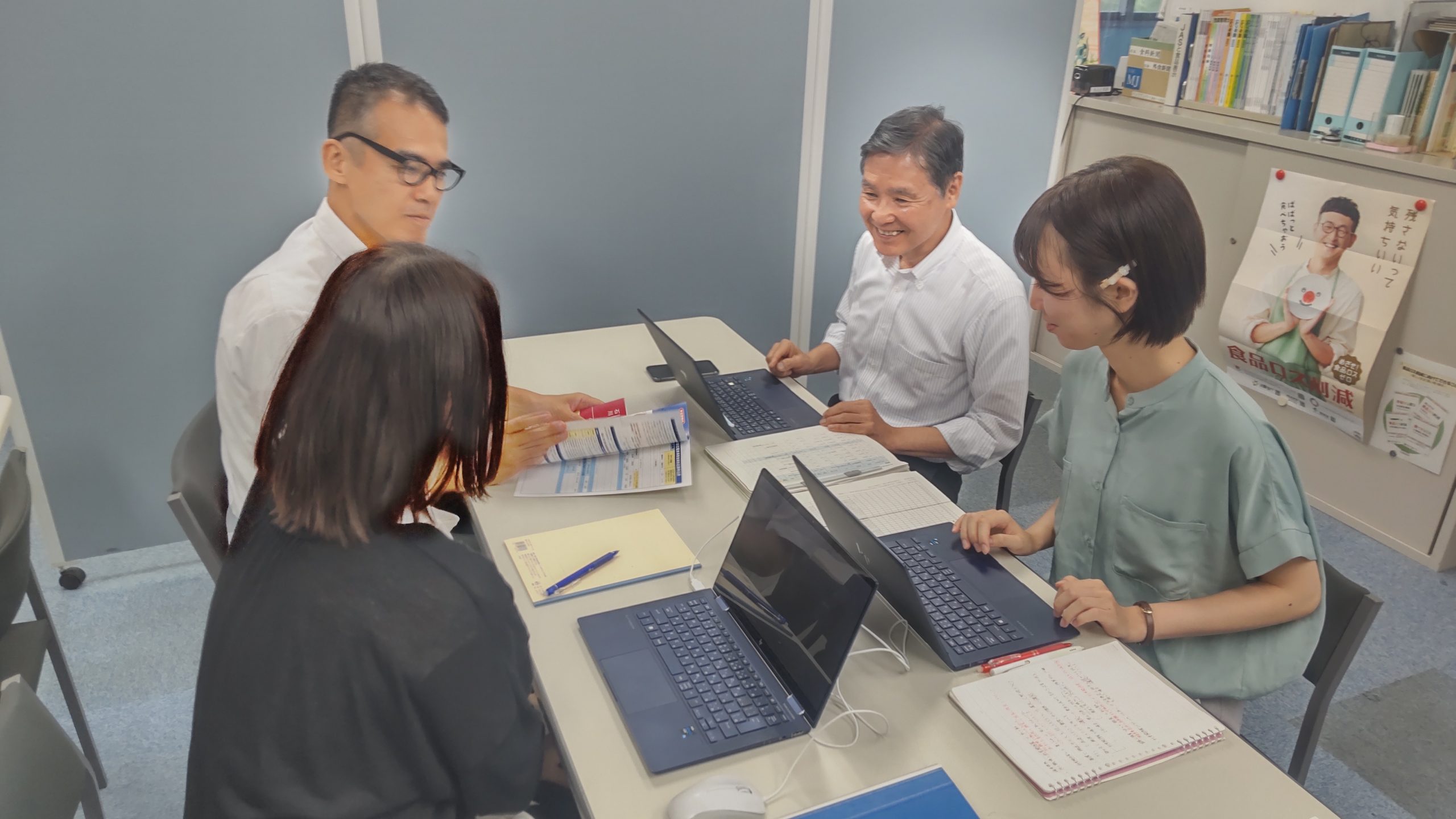
また、日本の国内市場が縮小し、小売側の交渉力が強くなっている今、中小の食品製造事業者が国内市場だけで生き残るのは難しいと感じています。輸出は成長戦略のみならず、そうしたリスクヘッジでもある。こうした“危機感”を持って真剣に輸出に取り組む必要があると、事業者と日々対話を重ねています。
輸出産地サポーターとしての役割、心がけていることはありますか?
東川
一番大切にしているのは生産者や事業者への「寄り添い」の姿勢です。単に「こうしたら良い」とアドバイスをするのではなく、生産者や事業者の目線で考え、一緒に輸出戦略を立てていくスタンスが必要だと思っています。中にはアドバイスを受けることに慣れていない事業者も多いので、ホスピタリティ精神を持って接し、相互の信頼関係を築くことが何より重要です。
また、単発の輸出ではなく、継続的な輸出ができるビジネスモデルの構築に向けた対策を考えることも意識しています。目的や戦略がないまま始めた輸出は、バイヤーが離れた時点で終わってしまいます。そうならないよう、経営戦略として「なぜ輸出するのか?そのために何をしなければならないのか?」を一緒に考えて、輸出への後押しをすることが、輸出産地サポーターの役割だと思っています。
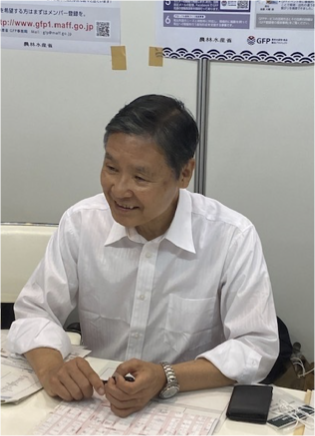
中でも印象に残っている支援の事例はありますか?
東川
いくつかありますが、印象深いのは複数の事業者が連携して輸出向けの新商品を共同開発した取組みです。一社だけでは突破できない壁も、得意分野の違う企業が手を取り合うことで可能性が広がり、中小の事業者同士が協力し合って輸出を始める一歩になりました。
また、ある生産者は、観光客向けに自分の畑にコテージを建て川から水を引き込み、カヌー体験まで提供する「農業×観光×滞在の複合型ビジネス」を構想しており、さらに輸出にも取り組みたいとのことでした。この生産者には、まず、複合型ビジネスを軌道に乗せ、事業規模を大きくして体力をつけてから輸出してはどうかと、中長期的な視点からアドバイスをしました。こうした挑戦をじっくりと支援することに、大きなやりがいを感じています。
副業・プロ人材など、多様な人材活用についての可能性は?
東川
正直なところ、専門性の高い人材をフルタイムで雇える事業者は少ないです。そうした余力のある食品製造業は、年商10億円を超える事業者だと思いますが、北陸地方では、そうした事業者は限られており、多くの事業者が費用対効果の面で雇用に二の足を踏んでいます。
しかし、輸出について、外部人材の知見は確実に必要です。だからこそ、フルタイムではなく、副業や派遣といった柔軟な関わり方で専門家が支援する仕組みには大きな可能性を感じています。事業者側も「こんな人がいてくれたら有難い」と思っている。そこをつなぐ仕組みを、今後はもっと広げていきたいですね。
最後に、輸出産地サポーターとしてのやりがいとはなんでしょうか?
東川
やはり、事業者と本音で話し合いながら一緒に可能性を探っていく過程に、非常にやりがいを感じます。自分自身が培ってきた知見や視点を伝えることで、「そんな視点は持っていなかった」「自社の強みに気づけた」と言ってもらえるのは嬉しいですね。
また、これまでのキャリアを通じて得た人脈を活かして、海外の販路開拓に困っている事業者を支援したり、どうやって海外展開を進めていけば良いのかわからない事業者にアドバイスを行うことで、事業者が積極的に輸出に取り組むようになってもらえることも嬉しいです。
事業者が「よし、やってみよう!」と一歩を踏み出す瞬間に立ち会えることが、この仕事の醍醐味だと思っています。
